![]() Googleマップ 熊野古道
Googleマップ 熊野古道

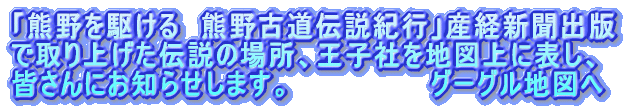

「 」をクリックしてください。地図が大きくなります。↓
さらに、上の地図を大きい地図で見る
グーグルマップ 「熊野を駆ける 熊野古道伝説紀行」産経新聞出版
平成27年4月
おことわり
古道の中で、特に山岳地帯では
グーグル社も表示できていない個所があります。
その地点の地図精度についてはご容赦下さい。

書籍の詳細は、下記のアマゾン、セブンイレブンでご覧下さい。
![]()
![]()
|
|
| Googleマップ 熊野古道 熊野九十九王子がどこにあるのか知っていますか? 旅行ガイドの地図、観光マップ 和歌山県発行の公式マップは便利ですよね。 でも、今どこにいるのかわからない? ええっと・・・・ この地図によると・・・・ ここどこ? ? うそー! ? わからない。 ??? せっかく熊野古道の地図を片手に歩いているのに 今いる自分の場所がわからない・・・。 旅先で迷ったことはありませんか? グーグル地図は、こうした時に便利です。 携帯電話、スマホ、アイフォン、アイパッドで 地図検索! 自分の位置を表示! 便利です。 私は、現在、安珍や藤原秀衡が熊野詣のため歩いたという 旧中山道や旧奥州街道を調査中です。 この時、地元の方が作成したグーグル地図は大変重宝しました。 この石碑はどこ? この遺跡はどこにあるの? グーグル地図を頼りに進むと・・・・・ 「え、えっ!」 目の前にその石碑があるではありませんか。 それも1メートルも違わない正確さで! 感動! 感謝! グーグル社の意図はこれにあるのですね。 一部の人が知っている情報を、 初心者の人にも、 土地を知らないよそ者でも・・・・ 強力にサポート! うーん。 さらに・・・。 この地図は、次の宿場町、王子社まで案内してくれます。 それも、リアルタイムに最新地図で・・ 線路や障害物は回避して、 交通不能の場所は迂回して、 最短距離を案内。 以前は、探し回って 結局分からず帰ることも・・・ 家に帰ってから資料を見直して。 またそこへ、探し回る。 こうした無駄が全くありませんでした。 これは、旧中山道を知り尽くした先駆者 先人、つまり先達たち 私のアイフォンは、御師や先達となって 「こう行くのだ。」 「そうだ。そこだ。」 「がんばれ!」 ・・・と言っているようでした。 地図作成者の知識の深さに脱帽です。 この出来事がきっかけで こうしたグーグル地図は、役立つとわかり、 ぜひ、熊野古道も知ってほしい。 熊野九十九王子を歩いてほしい。 和歌山に来てほしい。 そう思いました。 そこで、私が33年間かけて調べた資料を グーグル地図に表示することで、 若い方に知ってほしい。 そうです。 さらに、その土地で聞き知った伝説を聞けば 多くの先人達が どうして熊野に向かったのか 理解できるのではないでしょうか? それでは、よい旅を・・・ 大上 敬史  ◆ 追記 ◆ 熊野九十九王子については諸説があり、 また時代や文献によって異なります。 ガイド本、解説書でも違いますね。 私は、基本的に文献は信用しないタイプの人間です。 ひねくれています。 そのおかげで、文献の間違いをいくつも発見しました。 ある文献の研究者が記した記事を それを参考にした次の研究者の方は 同じように書いています。 古い文献になればなるほど 権威というか 皆一様に信用しています。 「文献にないから・・・」 「文献にそう書いてあるから・・・」 でも、誤字を解析するように 古文書は読まなくてはなりません。 例を挙げますと、有間皇子の変で 「留守官 蘇我赤兄」 と記す文献が多いのですが、 留守官 という官位があるわけではありません。 正しくは「留守宮」 官ではなく、宮なのです。 すなわち、斉明天皇が白浜に行き、 京の都、すなわち宮が留守になったので 「宮の留守を守っていた蘇我赤兄」 と解釈するのだと教えていただきました。 日本語は深い。 紙が貴重な時代に、先人達は 少ない文字で、次の世の人に 自分たちの思いを伝えようと必死でした。 その結果、編み出されたのが日本語という 外国語にはないツールです。 外国人にはわかりにくいようですが 一見、難解 非合理的のように見えますが、 音や言霊、祝詞、歌、詩歌 それは、他の言語にはない非常に深い意味合いを 結果的に持つことになったのです。 日本の歴史を知れば日本人の知性が 古文書にはにじみ出ています。 話がそれましたね。 熊野九十九王子自体、御師が指定した時代の流れから 観光要素的な、つまり今で言う地元の観光アピ−ル 利益、金銭的な要素もあったのかもしれません。 新王子は、時代の中で生まれました。 霊験とともに設定され、そこは信仰の対象となりました。 私が、書籍「熊野を駆ける」の中で、 「御師、先達たちは、その道すがらに罠を仕掛けた」 と書いたのも、 山伏は、修行をしていない帝や一般の者でも 早く、最速に熊野権現の意を会得できるように 王子社を設定したのだと仮説を立てています。 山伏は、石に術を仕掛けるようなことをしました。 それは、それに触れれば自ずと会得できるよう 王子社に詣でれば しだいに、位が上がるように 熊野権現に近づいて ついに熊野本宮、証誠殿の前で皆、額づいたのです。 こうしたことを理解しないと 王子社の位置、意味 罠・・・(いい意味の仕掛け) すなわち、御師や先達の意図を読み解かないと 分からないのです。 中国に そこに至れば龍が滝を登るように 術を知らない未修行者が 急に会得してしまう不思議な場所があると言います。 風水という形で伝来しています。 僧達が、風水の術を駆使したかは定かではありませんが 少なくとも王子社は、 風水の術で設定されていることは間違いないようです。 ですので、私も一般的な王子社の場所とともに いろんな説も排除しないスタンスでアプローチしています。 地図の王子社は、私の個人的な見解も含んでいますので、 信用しないで・・・・ 権威のある他の書籍と比べて下さい。(笑い) また、「道」についても王子社から王子社に単に行く というものではないと 読者の方も感じているのではないでしょうか。 現在、観光ガイドや公式地図に示されているのは 単に、今、適法?合法的に歩ける・・・・ という道でしかありません。 それは、王子社自体、私邸の中にあったり 道が、人様の敷地内を通過しているから、 迂回するしかないわけです。 このホームページをご覧の皆様は、 かなりディープで 熊野古道好きと拝察します。 すべてを言わなくとも、 もう、おわかりと思います。  拝謝! |